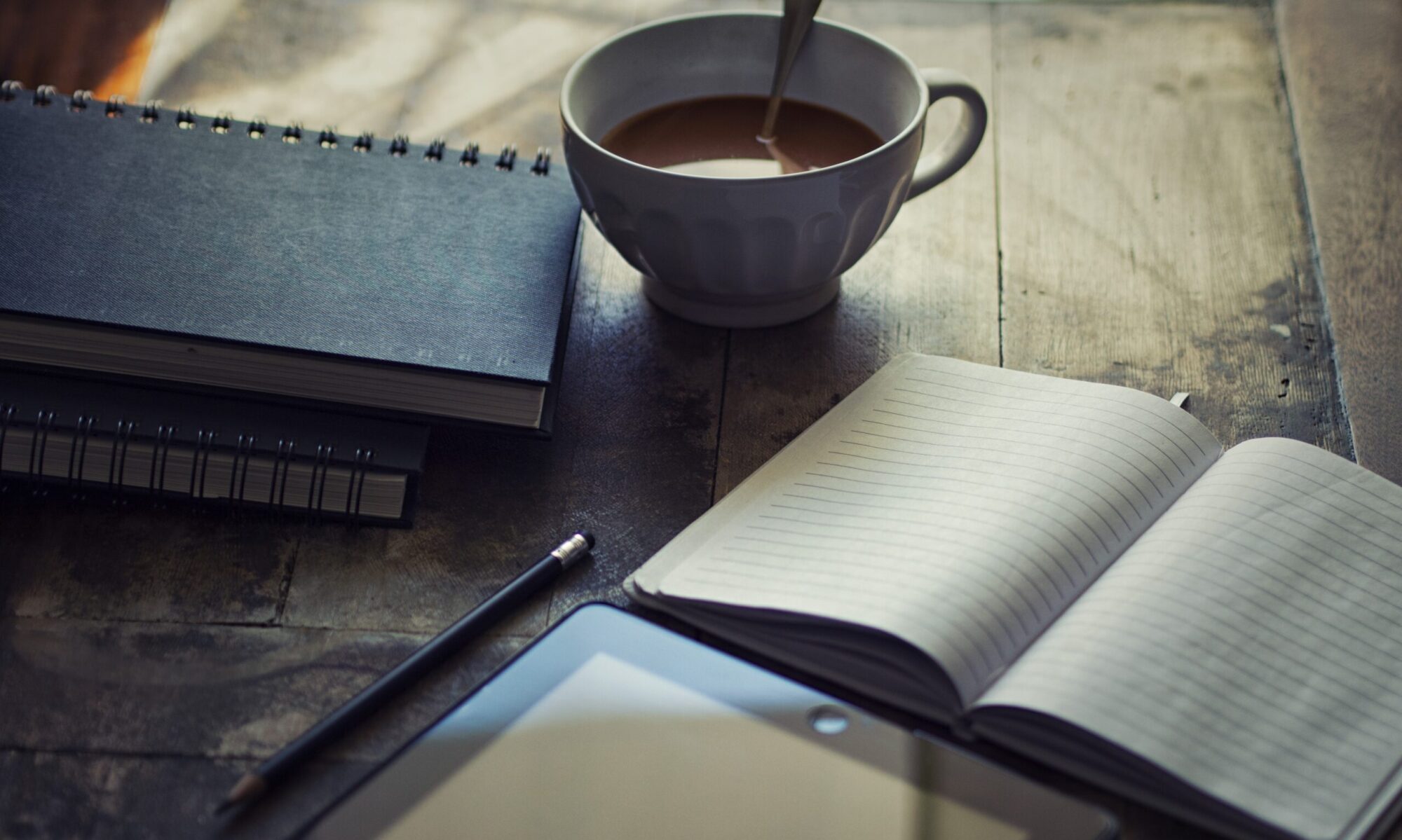人は、「会社を興そう」、「英会話を始めよう」など、何かをやろうと奮い立つ時には、ほとんどの場合何らかの動機があります。今回は、この動機に関することで欲求の本質に迫ってみたいと思います。
動機づけという観点から見た場合、人は大きく2つのタイプに分けられるといことです。ひとつは、問題回避型、もうひとつは目的志向型です。これは、ドイツのグスタフ・フェヒナーの快楽原則という考え方から導かれたタイプ分けのようです。
問題回避型とは、将来起こり得るリスクに対して、それを回避したいということが強い動機付けになるタイプです。
たとえば、化粧品については、「今から小じわの手入れを始めておかないと10年後は、大変なことになりますよ」というようなトークをされるとリスク回避スイッチが入り、その化粧品を買ってしまうようなタイプです。
これに対して目的志向型は、将来に対する不安感にはあまり反応しない。それよりも、「美魔女になり、街で振り返られる自分を想像してみませんか」というようなトークにスイッチが入り、そのためなら、と化粧品を買ってしまうタイプの人です。
この2つのタイプのことを知っていれば、相手のタイプによって営業のトークを変え、それにより成約率を高めることが可能となるわけです。
なお、このタイプは、どちらが良いというものではなく、単なるスイッチが入るツボの違いということです。
この動機づけのタイプは、本能的なものであり、欲求の本質のひとつ側面と捉えることができると思われます。
新規事業の企画を通すには、当然、意思決定者の承認を得なければなりませんが、その人のタイプを知っておくことは大切かもしれません。たとえば、新規事業に取り組む目的の論理展開を問題回避型と目的志向型によって、変えることは有効かもしれません。あるいは、新規事業のテーマもタイプによって選ぶことも大切かもしれません。たとえば、“保険”という商品は、問題回避型の人の方が、スイッチが入りやすいと思われます。このように、商品特性も踏まえて提案することが、企画案を通す確率を高めることにつながるかもしれません。