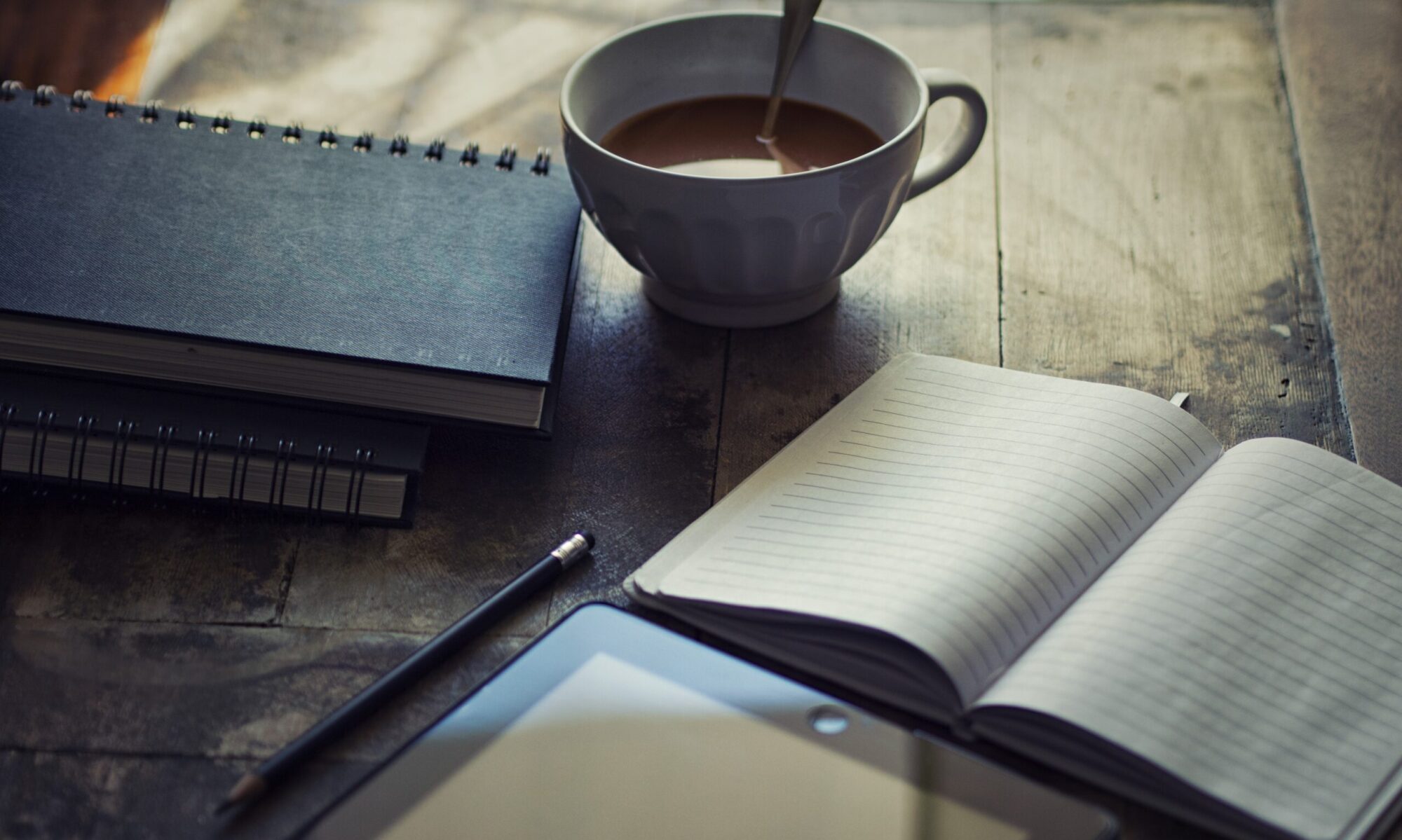「隠れ家レストラン」や「隠れ家バー」などの言葉は、情報雑誌やファッション雑誌ではよく見られます。繁華街ではない、ひっそりとした住宅街や路地裏などの目立たない場所にあり、“知る人ぞ知る”というような店舗のことです。
「隠れ家レストラン」と言われる店舗は、何となく魅力的に感じる店舗であり、お馴染みなったことを自慢できそうな感じがして、「一度行ってみたい」と思いたくなります。
しかし、ちょっと視点を変えてみると、「隠れ家レストラン」はあっても、「隠れ家コンビニ」はありません。「隠れ家銀行」と言われるような立地にあって、融資が増えた銀行があるという話も聞いたことがありません。
何故、レストランやバーなどの飲食店は、“隠れ家”があるのに、小売店やサービス店は、“隠れ家”がないのでしょうか。今回は、このことについて、Deep Thinkingしてみたいと思います。
一般に、店舗は、立地条件の良い場所に出店することが、繁盛するための最大のポイントと言われています。すなわち、「ほとんど立地で決まる」ということです。ところが、飲食店の場合は、この法則が当てはまらないこともあります。というのは、飲食店に限っては、場所が悪くても、おいしいものであれば、わざわざ遠くまで食べに行きたいという動機をいただかせるパワーがあるようです。
たい焼き屋にも“東京御三家”があるようですが、四谷にそのひとつのたい焼き屋があります。平日の昼間に行っても、たい焼きが焼けるのを多くの人が並んで待っています。ひとつだけ買う人もいれば、30個買う人もいます。30個も買うということは、たまたま見つけたたい焼き屋ではなく、たい焼きが目的で、この店に来たのです。
10月になると、上海蟹を食べるためだけに上海へ行く、という人もいるようです。どうも人は、おいしいものを食べるだけで幸せを感じ、おいしいものを食べたいという欲求は、様々な欲求の中でも、かなり強いことが想像できます。
不便な場所にあるコンビニに、敢えて行くことは基本的にないようです。不便な場所にある銀行も同様です。しかし、このような不便な店舗でも、オリジナルのおいしい食べ物をサービスで提供する、あるいは、オリジナルのおいしい食べ物を販売するなどのサービスを付加すると、とたんに、「わざわざ行く店舗」に様変わりするかもしれません。
それほど、“おいしい”を味わいたい欲求は強いということです。