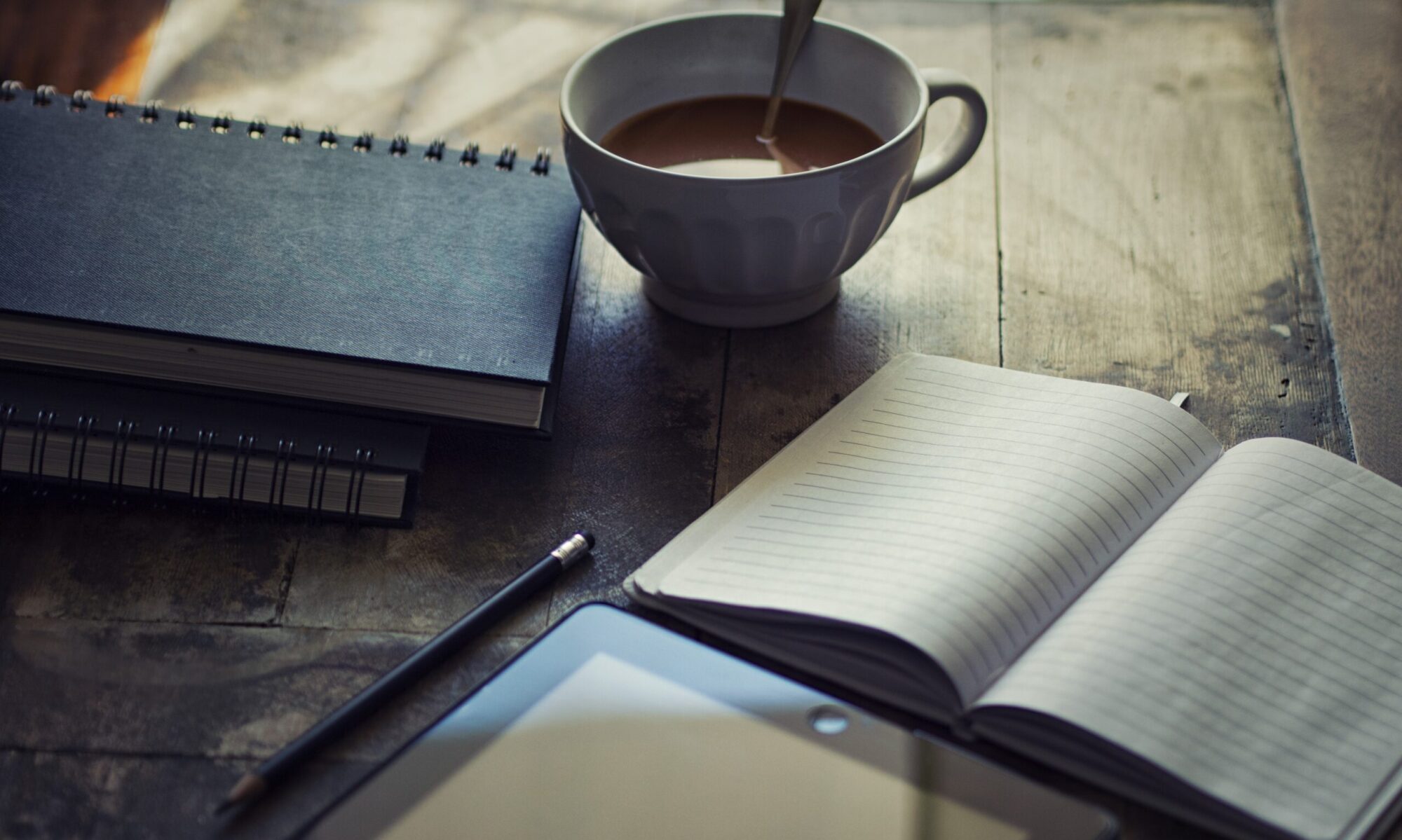ネットの世界の仮想都市空間に入り、仮想の生活を送るという米国発の「セカンドライフ」というサービスが流行り始めています。先日、SBI(ソフトバンクインベストメント)も、この分野の事業に参入するという発表がされていました。
今回は、この仮想都市空間について考察してみたいと思います。
仮想都市空間では、アバター(自分の分身)を登場させ、そのアバターが生活できるように、仮想都市空間内に、土地を買い、住宅を建て、服などを買います。そして、自分のネット上の家にネット友達を招きい入れ、会話をしたりして遊んでいきます。
私も子供の頃、人生ゲームというボードゲームでよく遊びました。祈りながらルーレットを回したこと、ゲームの最後には、産んだ子供をお金で精算することに違和感を覚えたことなどを思い出します。
人生ゲームも、自分の人生を仮想の世界で展開していくという点では、仮想都市空間と似たところがあります。しかし、どこか違っています。では、違っている点はどこでしょうか。
人生ゲームは、ご存知の通り、1から10まで(だったと記憶していますが)の数字が書いてあるルーレットを回し、その出た数によって人生が決まっていくものです。すなわち、自分の意思に関係なく人生が決まっていきます。
一方、仮想都市空間は、年齢、性別、職業などのアバターのプロフィールを自分で決めていき、仮想の世界で友人関係をつくり、気に入ったものをネット上で購入していくものです。
すなわち、人生ゲームは、意思とは関係なく自分の人生が決まってしまうのに対し、仮想都市空間は、自分が主体的に人生を決めていくということが大きな違いと思われます。
また、もうひとつの違いは、人生ゲームは、順位を決める競争ゲームであるのに対し、仮想都市空間は、競争ゲームではないということです。
では、競争ゲームではない仮想都市空間は、何が楽しいのでしょうか。
それは、イマジネーションではないかと考えます。
人は、理想とする地位、好きな人物(ヒーローなど)、あるいは興味のあるプロフィールになって、その立場から人生を試してみたいという欲求を持っているのではないかと推察します。
しかし、何故、そのような欲求を持つのでしょうか。それは、なりたい人物になった時のことを想像して、楽しんでいるからではないでしょうか。すなわち、イマジネーションを楽しんでいるのです。
仮想都市空間は、想像欲を刺激するサービスに、なっているのではないでしょうか。